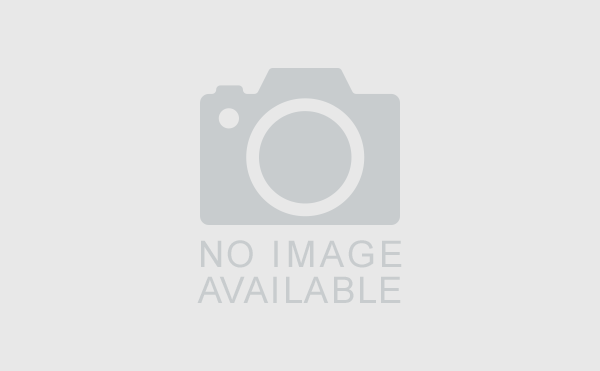特に醤油で「丸大豆」と表現できるものは少ない
天然醸造と表現できる醤油は、国内でもわずか1%ほどしかないという説明をしましたが、次に表現されている言葉で大切なのは「丸大豆」という言葉です。じつはこの言葉もとても尊いのです。現在の日本の醤油で丸大豆使用と表現できるものは約18%だといわれています。それ以外の82%の醤油では「丸大豆醤油」とは表現できないのです。原材料が大豆ならどうして?と思うでしょう。
大豆消費の多い日本食、だけどほとんどが輸入
日本はアメリカやブラジルから大量の大豆を輸入しますが、もともとそれらの国々は味噌、醤油、納豆、豆腐などの大豆を食べる食文化は少なく、何のために大豆を大規模に生産しているかといえば、その目的のほとんどが油を搾るための大豆なのです。さて、その大豆を搾った搾りかすは産業廃棄物ですが、もともとは家畜のエサにしたり、有機肥料として畑に還元したりするのが基本でしたが、日本なその大豆の搾り粕を大量に輸入して、それをもとに醤油を仕込んでいます。
産業廃棄物でつくる醤油?
大豆油の搾り粕なので原材料は大豆ですが、その姿は丸々とした大豆ではなく、つぶされたフレークの状態ですから「丸大豆」と表現できないのです。丁寧なメーカーさんになれば裏の原材料表示には脱脂加工大豆と明記されます。
それは、決定的な味の違い
当然丸大豆よりも安く製造できます。安い醤油の根本的理由は、原材料の安さと熟成時間の短さが決定的になっています。製造メーカーさんによれば醤油を製造する過程では油分は必要ないから都合がよいともいわれることがありますが、本来の大豆の美味しい部分を除いた原材料では、それが本来の味になるかどうかという疑問があります。
味の比較では脱脂加工大豆を利用した醤油はキレがあるのに対し、丸大豆醤油はまろやかなコクがあるといわれます(油脂成分が醸造中にグリセリンなどに分解されて旨味とコクにつながる)。この比較には好みもありますからなんとも良し悪しの判断はできないかもしれませんが、安全性ということから見た場合、脱脂加工大豆は石油由来の溶剤で処理されることがあり、その有害物質が残留する可能性があると指摘されています。
味噌の場合は比較的、丸大豆を使用していることが多いそうです