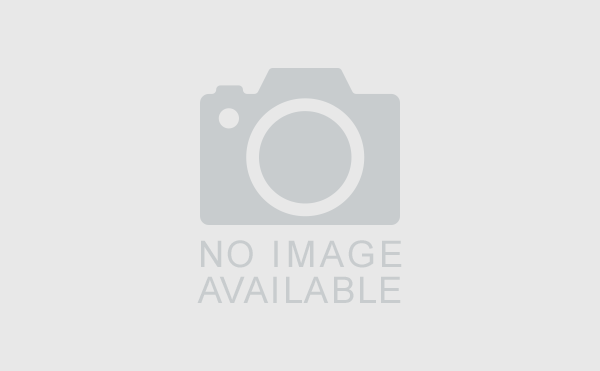味噌は、最も良い非常食になる
保存食である発酵食品は私たちの命をつなぐ大切な存在
手作り味噌のメリットは色々あります。そのひとつに常温で長期間保存できるということです。味噌の熟成は常温です。
常温だからこそ菌たちが働いて美味しくさせるし、ある程度完成されたあとも、常温で大丈夫です。冷蔵庫に入れる必要はありません。ここが大切なポイントです。
保存といえば、冷蔵庫が当たり前の時代ですが、電気がなくなったら・・・
私たちは冷蔵庫で食品を保存するのが当たり前な時代に生きていますが、もし何かの災害や社会的異変が起きてしまった場合、電気をもとにした便利快適な生活ができなくなるようなことも、いつおきてもおかしくない時代です。さらに流通が止まって、食料の運送が途絶えて、スーパーマーケットのお店に行っても食べ物がなくなってしまうなんて恐れもあるかもしれません。
そんなときに、冷蔵庫の物がすべていたんでしまったとしても、味噌だけは常温で大丈夫です。その味噌には材料となっているお米の栄養、大豆の栄養、そして人にとって欠かせない大切な塩分が全てバランスよく含まれています。食べ物がなくなった時でも、人は保存されている味噌を少しづつ食べて、そのときにとれる季節の野菜か山菜などを食べていれば最低限の飢えはしのげるのではないでしょうか。
野菜の保存は乳酸発酵お漬物で
漬物もまた野菜を乳酸発酵という方法で保存してきた大切な方法です。漬物は発酵の過程で生まれる乳酸という物質が野菜の保存性を高めて、腐敗することなく雑菌が増えることなく蓄えることができます。雪国で漬物文化が盛んになったのは、雪国の生鮮野菜のない冬の食料を確保して、厳しい冬をいかに乗り越えるかという難題を解決する大切な方法だったのです。
災害や食糧難を乗り越える力になる
このように日本では発酵食品による保存食を常備しておくという文化がしっかりと根付いていたからこそ、どんな天候不順や時代的な変動をも乗り越えてこられたのだと思います。例えば江戸時代には「天保の飢饉」と言われたほど、異常気象による作物の極端な不作による飢餓を経験したといわれています。江戸時代後期の1833年から数年続いたとされるのですが、おそらく大雨や冷夏などによるお米をはじめとする食料の凶作による食糧危機だったそうです。特に東北地方はお米の収穫量が90%減少したとか。その時の餓死による死者数は日本全国で約20万人規模だと伝えられていますが、実数はそれほどではなかったと私は推測しています。人々の食料を支えていたのは発酵食品の保存食が命の下支えになっていたはずです。
近年、鈴木宣弘(東大・経済学者)の推計によれば今後日本には迫りくる食糧危機があり、極端な災害や天候不順による凶作ではなくとも、世界的な経済や戦争などの混乱による日本にくる飢餓を懸念し、今のままの日本の食料自給率では、日本人の約7200万人が餓死するという推計を発表されています。それは世界の約1/3の餓死者は日本に集中するという事態です。過去の江戸時代の飢饉とは比べ物にならないほどの規模の飢餓の恐れを目の前にしているのかもしれません。近代日本には本当の意味での保存食や備蓄食料というものはとても少なく、各家庭単位で備蓄されている食料は皆無といってもいいほどだからでしょうか。
【参考図書 鈴木宣弘著書『世界で最初に飢えるのは日本』(講談社+α新書)】
今、私達が大切にすべきは、本物の保存食としての発酵食品の復興です。
食料の備蓄を国や大きな倉庫に頼るのではなく、各家庭という最小単位のなかで常に食料を備蓄しておく営みが大切なのです。大切な方法を私達に教えて頂けているのは、昔からのあたりまえの日本食文化であって、本物の発酵食品づくりの文化のある、本来の日本の姿そのものではないでしょうか。