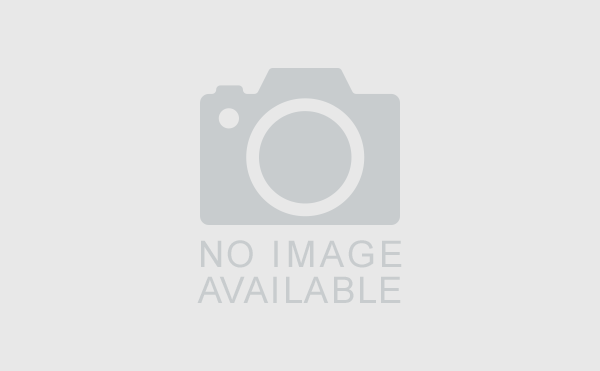味噌の熟成は、いつまで美味しいの?いつまでもつの?
熟成の味は格別ですね
例えば、煮豆のままの状態ではおそらく2日くらいで、食べられない状態に傷んでしまいます。その煮豆を適量な塩を混ぜ、味噌として仕込んだ場合は腐敗することなく保存がききます。仕込んで1年たったものは香りが良く、2年たったものは味も深みがあり、3年にもなると味わいに深いコクが生まれてきます。醤油と味噌は同じ傾向にあります。人によって好みの差が大きいことではありますが、1年熟成の香りが良く軽やかな味噌が好きな方もいれば、3年熟成のコクと旨味と深みが増したようなズドンとした重みのある味噌が好きな方もいらっしゃいます。
3年くらいまでが美味しい、あとは好み次第
食べて大丈夫かという食品の安全性とい点でいえば、状態としては10年でも保存ができるかもしれませんが、実際は3年くらいの熟成が美味しさの限界ではないかと思います。
年数が経過するほど味噌の持つ水分が蒸発してゆくので、3年以上過ぎたころからは、しっとりとした風味が失われて香りも低下し、パサパサしたような感じになってしまいます。
例えば、梅干しは?
熟成が増すほど価値があるものと言えば梅干しがあります。当然梅干しはある程度水分が抜けても大丈夫ですし、年月が経つほど価値があり、まるで薬効がでるといわれるほど未知なる力を発揮しはじめるそうです。
漬物はいつまで熟成なの?
梅干しとは違って、野菜の漬物の場合はどうかといえば、長くて1年、もしくは2年ほどでしょうか。もともと毎年季節になれば、旬の野菜は収穫されるものですし、サイクルが短いため長年保存しておくという理由もメリットも発揮されにくいものです。
漬物の目的は、旬でしか収穫できない野菜の保存性を高めて長期間食べられるためのもの。もうひとつの目的は、乳酸発酵によって素材の野菜以上の美味しさを引き出し、栄養価を高めるためということにあります。発酵食品の目的や用途によって、発酵のさせ方もいろいろあるのが面白い世界でしょう。
糠漬けのように数日で漬け上げるのもよし。たくあん漬けのようにじっくり熟成させるのもよし。用途や味、目的によって解釈は幅広く発展してゆきます。定義はないということでしょう。