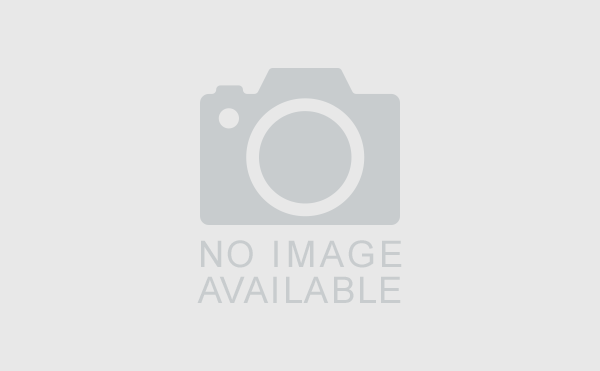さあ、味噌づくりの実践
では、実践の味噌づくりです。さっそく味噌づくりをしてゆきましょう
(この記事は、実際の味噌づくり講座の場面を記録しました。)
大切な分量
材料のうちの大豆。まずは順番でゆくと似た大豆をつぶしてゆきます。今日は1㎏の味噌ができるための大豆をあらかじめ袋に取り分けています。1㎏の味噌ができるための煮豆の量は約630gです。これは乾燥大豆のときの重さでいうと約250gです。先ほど説明したように乾燥大豆は水を吸って、じっくり煮て膨れて重さがずっと重くなっています。
2kgの場合はこの袋を2つということですね。
大切な順番① 煮た大豆をつぶす
さて、この煮豆をどうやってつぶすかというと、この煮豆を何か容器に入れてつぶそうとすると、豆があちこちに飛んで行ってどうも難しい。大変なことになるので、この袋のまま上からぎゅっと押しながらつぶしてゆきます。するとみるみるうちに潰れてゆくでしょう。ぐいぐいと力をこめてつぶしてゆきます。ではやってゆきましょう。
そこで、どこまでつぶしたらいいの?と思いますが、これは2年前に仕込んで出来上がった味噌です。よーく見るとこのようにお豆がそのままの形で残っているじゃないですか。豆が残っていても味噌にはなるのです。先ほど水煮の豆を食べていただきましたが、次はこの味噌になった豆を食べてみましょうか。煮豆も美味しかったけど、味噌になった豆は、はるかに旨味とコクが生まれて美味しいでしょう。このように豆が残っていても味噌にはなりますが、豆の形を残すか、今完全につぶすかは好みです。豆が残っていても味噌になったときに、味噌漉しなどでつぶすかどうかの違いです。今頑張ってしっかりつぶしたら完成もなめらかな味噌になりますね。この味噌になった豆も美味しいから、ちょっとしたおつまみになるということも楽しみになることもありますよね。
グイグイとつぶしてゆきましょう。
ずいぶんと潰れてきましたね。
大切な順番② 糀の塩切り(塩と糀を混ぜること)
では、次の工程に移りましょう
糀の塩切り。糀と塩を混ぜることを言います。塩こうじを作ったことがある方は経験があると思います。
大豆はあらかじめ分量を量っていましたが、全て私が分量を量っていると、楽しいところ全部私が準備するといけないから、次は糀の量を量っていただきましょう
1㎏の味噌ができるための糀の量は250gです。今回は2㎏の味噌ですから糀の量は500gですね。
大切なポイント、塩の量の計算・・・間違うと失敗のもと
次に残った最後の材料は塩。
塩の量が今回とても大切です。13%の塩分の味噌を作りますが、その13%はどのように図りますか? これは、つぶした大豆の重さと、糀の重さの合計の13%です。
ではつぶした大豆の重さを量ってみましょう。
2㎏分の味噌で、つぶした大豆の重さは1260gですね。それに糀の重さは500gで合計は1760gです。この重さの13%は、1760g×0.13です。答えは、229gの塩を入れると13%の塩分の味噌ができるということです。
さて、けどもこの計算が合っているといえば合っているけど、間違っているといえば間違っているのです。私が計算を誘導しておきながら、間違っているって??と、おかしいと思いませんか。もう少し詳しく言いますと、この食塩という塩の場合はこの計算が大正解なのですが、今日使う塩のシママースという塩を使った場合はこの計算ではちょっと間違っているということなのです。さて、何が違って何が間違っている原因だと思いますか?
二つの種類の塩ですね。何が違うのか、ひとつめの食塩は精製塩と言われる塩。ふたつめ
は天日塩と言われる塩。パッケージだけ見ると、どちらも良いこと書いていますね。食塩のほうは、「国産、徳島県の海からできた」。天日塩のほうは「沖縄の塩」、「メキシコまたはオーストラリアの天日塩と沖縄の海水で作りました」。パッケージデザインだけをみると、国産のほうがいいのかなぁ。メキシコまたはオーストラリアの天日塩って大丈夫なの?これだけではどちらが良いのか、違いがはっきりわかりません。
見るべきは、塩の成分量
大切なのは塩の成分です。今は食品には栄養成分表示ということが義務表示になっていますが、この表示を確認してみましょう。
食塩をみますと100gあたりンパク質、炭水化物いずれもゼロですね。食塩相当量99%。ほかの成分がゼロだからほぼ純粋な塩そのもの。塩だから当たり前だと思われるかもしれません。
では、次に天日塩を見てみましょう。同じく100gあたりタンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量93.2g。カルシウム190mg、カリウム110mg、マグネシウム150㎎となっています。
精製塩と違うのは食塩相当量がずいぶんと違います。ほかに入っているものはカルシウムやカリウム、そしてマグネシウムなど、そのほか書ききれない海のミネラル成分がたくさんあって、食塩相当量が93.2gしかない。どちらの塩も真っ白で塩そのものにしか見えませんが、成分的にはかなり違いがあって、天日塩のうち7%は塩ではない海のミネラルが入っているということになります。ということは、さきほどの計算のまま13%の塩分を目指して計算して量った塩の量は精製塩の場合は確かに13%の229gの塩で正解ですが、そのままの計算で天日塩を229g入れると、じつは塩分相当量から見た場合7%ほど少ないということになってしまいます。
天日塩を使う場合の計算は、13%の塩分を量ったつもりですが、計算的には不足するので、足りない分の7%を割り増しで入れなくてはなりません。計算としては229g×1.07=245gとなります。
精製塩の場合の塩分計算
(つぶした大豆の重さ + 糀の重さ)×0.13=塩の量
天日塩(シママースの場合 食塩相当量93%)
(つぶした大豆の重さ + 糀の重さ)×0.13×1.07(食塩相当量93%のとき)=塩の量
*天日塩の種類によって食塩相当量の含有量は全て大きく異なります。使う塩の塩分含有量を確認して、不足分を足す計算の数値が異なってきますので注意しましょう。