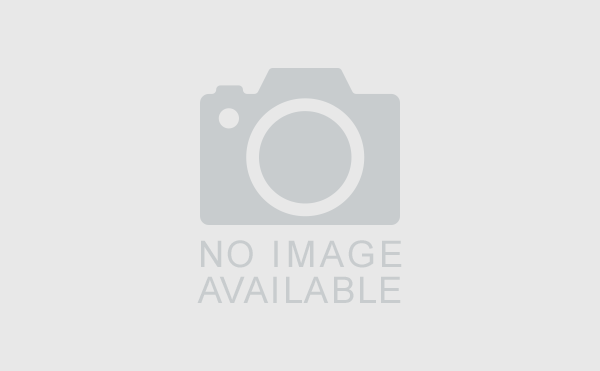減塩味噌は失敗のもと
減塩味噌になったときに、どうして失敗するのか?
減塩味噌になったときに、どうして失敗するのか?
減塩味噌を作ろうと試みたり、正しい計算で塩分量を計算せずに減塩になったとき、私は「失敗して残念なことになるから、減塩味噌はやめたほうがいい」と止めることがあります。どのように失敗するのでしょうか。
味噌が美味しく熟成されるためには菌たちの働きがとても大切だという話をしてきました。では菌は菌でも、少ない塩の環境で元気よく働く菌たちはどのような菌だと思いますか?味噌を熟成させるときに働く菌とは種類が違うのです。少ない塩で活発に働く菌とは・・・?。
答えは漬物です。漬物の場合は塩分が約3~5%くらいが標準的です。味噌は約13%以上の塩分になりますからずいぶんと低い塩分です。さて、漬物を美味しくさせる菌といえば、馴染みのあるのが乳酸発酵の乳酸菌ですね。では、味のイメージはどうでしょうか。乳酸菌の乳酸発酵といえば、「酸っぱい」ですね。酸味があります。
減塩すると、美味しくない。酸っぱい味噌になった~!?
減塩味噌をつくったときに起きるトラブルはこれです。1年熟成して菌たちも働いてくれたきっと美味しい味噌のはずと思って、手作り味噌で、はじめての味噌汁をつくったときの一口目の感想といえば「酸っぱい!いたんで、わるくなった訳じゃなくて、出来立て味噌汁なのにどうしてこんなに酸っぱいの?!」という残念な結果になってしまうことがあります。
これは、味噌の熟成のときに乳酸菌たちが元気に増えて働いてしまった結果です。味噌の熟成には乳酸菌や酵母菌の働きが大切になってきますが、乳酸菌はあくまで脇役で主役ではありません。味噌の熟成に働く菌は主に耐塩性の酵母菌です。さらに麹菌が生成した酵素が成分の分解にはたらくのです。
大切なのは菌の種類です。味噌の発酵過程では確かに乳酸菌も必要になりますが、それは乳酸によって酵母菌が発酵しやすい環境が整うのが目的です。多くの乳酸菌は塩分10%以下で旺盛に繁殖します。したがって塩分10%以下の減塩味噌では乳酸菌たちが主役になってしまいがちなのです。
日本人が味噌づくりを昔から行ってきて経験的に失敗のない塩分濃度を見出してきたのが塩分濃度13%以上というのは意味があります。
減塩したいときは、使う味噌の量を減らせばいい
もし家族で腎臓病などがあるために減塩をしなければならない場合には、しっかりとした塩分の美味しい味噌を作って、実際に味噌を使うときに、使う量を減らすようにする減塩をおススメします。
塩分のコントロールで食品の保存性がかわってきます。約10%以下塩分濃度の味噌の場合は半年くらいで食べ始めることができますが、味が美味しく保たれるのは食べ始めから約半年以内が目安です。塩分濃度13%の標準的な味噌の場合は1~2年で完成し、さらにそこから1~2年は美味しく食べられます。さらに15%以上の塩分濃度の味噌になれば保存性はさらに高まり3~5年でも安定した味の状態を保ちます。
大切な塩のはたらき、塩の力で菌をコントロール
塩には脱水作用と防腐作用があります。塩の濃度のコントロールによって繁殖出来る菌と、繁殖できない菌があります。主に腐敗させる菌や食中毒をおこすような菌の多くは塩に対しては弱い傾向にあります。塩を用いた食品は、効果的に保存性が高まります。さらにその濃度によって働く菌が異なってきます。
市販の味噌や醤油で減塩をうたった商品がみられますが、確かに減塩ですが、じつはそれらの食品の多くは食品添加物が多く使用されていることが多いのが実情です。それは、保存性を高めるための塩を減らすと保存性がなくなるから、保存性を高めるための科学的な保存料が必要となりますし、本来の発酵熟成が達成されにくい結果、味をコントロールするための化学的な調味料(アミノ酸等)を用いられていることが多くみられます。健康のために減塩商品を選んだはずが、目的とは逆に食品添加物を多用した食品をとることで健康な体作りとはかけはなれてしまうような、本末転倒な結果になってしまいます。