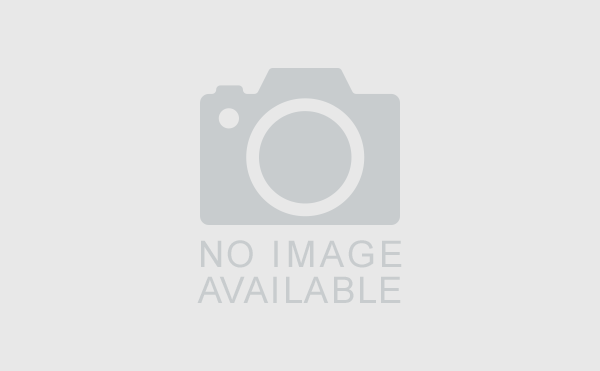料理の種類によって、使い分ける塩の種類
料理の場面では塩は欠かせないものです。醤油や味噌に含まれている塩分のほか、直接塩そのものを使う場面も多いと思います。味のベースになるのはもちろん、シンプルに素材の良さを引き出すための塩味や、最後の塩の一振りで整えるような場面などがあります。塩の品質で料理の個性が引き立つので、料理においての塩選びはとても大切な要素になるでしょう。
にがり(塩に含まれるミネラルとして)の害を知る
天日塩に含まれている「にがり」は、タンパク質と結合して食品や身体を構成するタンパク質を凝固させる作用があることを説明してきましたが、これは料理においての塩選びにも大切に関係してきます。
にがり成分がタンパク質と結合して凝固すると想像すると、料理の場面ではどのようなことが想定されるでしょうか。肉や魚の料理です。例えば肉料理なら焼いている途中に塩をふりかける。焼き魚も、はじめに十分な塩をつけて塩焼きするなどでしょう。化学的反応からみたら、にがり成分を多く含む塩を用いた場合は、それら素材のもつタンパク質に反応して若干ですが表面から凝固がおこります。そのため、にがり成分を多く含む天日塩の多用はあまりお勧めできないことになります。精製塩ならよいのかという単純な導きを言いたいのではなく、肉や魚の調理には、岩塩などの、にがり成分がほとんど含まれていない自然結晶の塩を使うことをお勧めしたいと思います。
肉や魚にはミネラルが少ない岩塩を、味噌や醤油には天日塩を、
にがり成分の反応からみた場合は、このような理屈が成り立ちますが、肉や魚などの余分な水分を出して肉を引き締めるための塩は、溶けやすい微細粒な塩を選ぶほうがよい場合もあります。岩塩は比較的粒子が大きいために溶けにくく、素材を引き締める効果はあまり期待できません。料理の過程の目的によって塩を使い分ける工夫が大切でしょう。たとえば、肉を引き締めるためには天日塩でも特ににがり成分が少ない塩を用いて、次に焼く段階になったら、肉の味をひきたてて、奥深い塩味をもたらす岩塩を用いるというように段階的に塩の使い方に変化をもたらす工夫をおススメします。
料理には直接つかうのはトータルバランスで美味しさを
逆に、塩おむすびや、野菜の調理、そしてお漬物などには、にがり成分を含む天日塩を用いることによって、複雑なミネラル成分を深みのある美味しさと感じることがあります。また単純な塩辛さだけの塩味ではなく、塩の結晶構造としてみると塩分(塩化ナトリウム)の結晶が多種多様なミネラル成分に包まれているようなイメージであることから、ダイレクトに舌にくる刺激的な塩辛さではなく、まろやかな塩味として感じられるのも特徴です。野菜などの素材の味を引き立ててくれる大切な塩となるでしょう。ただし、前述のとおり、にがり成分を多く含む塩の多用は身体に害をもたらすことがあると知ったうえで、極端に天日塩偏重にならないように、料理の種類によって塩を使い分けるという一工夫が、より一層美味しい料理づくりにつながるのではないでしょうか。