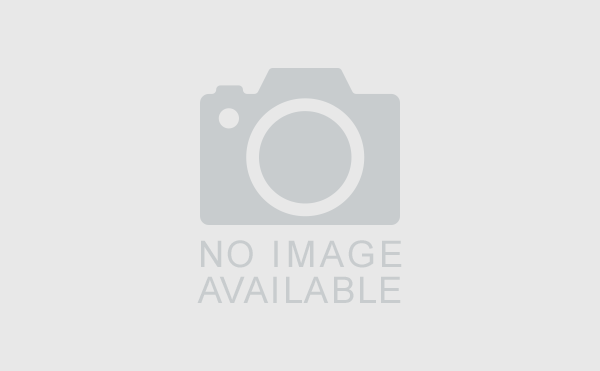老舗の蔵付き酵母を、「私の酵母」に継承
味噌づくりワークショップでの風景のなかから、
正しく塩分計算はできましたか?
糀と塩をまぜてゆきましょう。これを「糀の塩切り」といいます。塩こうじをつくるときと同じですね。糀のかたまりが、バラバラになって、お米一粒一粒に塩がまんべんなく混ざって均等になってゆくイメージで混ぜてゆきます。
ある程度まざりましたね。
ここで、この1年熟成した味噌を少しいれましょう。量は1㎏の味噌ができるためには中さじ1杯(約10g)くらい入れます。これを私は「タネ味噌」と呼んでいます。どんなタネかというと、菌たちのタネです。
タネ味噌を入れて仕込む~老舗の蔵付き酵母の再現~
味噌を仕込むときに、少しの量のタネ味噌を入れます。種はタネでもこれは、美味しい味噌ができるための菌を入れるときのことをタネと呼んでいます。それには1年以上熟成した完成した味噌をタネとしますが、このタネ味噌のなかには1年かけて味噌をじっくり美味しくさせてくれた菌たちが勢ぞろいです。
いわゆる熟成の季節ごとに働く多種多様な菌たちの宝庫としての働きをもたらします。もちろん、このタネ味噌を入れなくても味噌にはなりますが、入れるとより良い環境が整うということになります。イメージとしては、仕込みが完了してからの熟成のスタートのときに、味噌を美味しくするための菌としての選手たちがスタートラインに勢ぞろいというような雰囲気です。
老舗の蔵付き酵母
よく老舗の味噌屋さんや酒蔵などは「ここの蔵は独特な良い味だなぁ」ということを聞き、実際に味わったことはありませんか?これは歴史のある蔵ほど特徴があるのですが、その蔵の天井や壁、そして木桶などにもともと住み着いている菌たちがいて、その菌たちが味噌やお酒の仕込みのときに舞い込んできて、熟成に働くことで、その蔵の独特な味を醸し出してくれるからだそうです。主に酵母菌の種類が多いそうですが、蔵に住み着いている酵母菌なので、昔からそれらの菌は「蔵付き酵母」と言われてきました。
その蔵付き酵母は何か特別なことだと思ってしまいますが、そうではなく簡単なのは、タネ味噌をいれることによってその蔵付き酵母の働きが再現できるのです。飛騨高山よしま農園の味噌づくり講座では、20年以上活かし続けてきたタネ味噌を仕込みのときに少量入れます。講座の特別プレゼントです。
飛騨高山よしま農園は木桶による乳酸発酵お漬物の製造元ですが、これもまた木桶にすみついている桶付き乳酸菌たちが美味しいお漬物づくりに貢献していると私は確信しています。
市販の味噌はタネ味噌にはならない
蔵付き酵母としてのタネ味噌の良さがわかったと思います。手元にそのタネ味噌がないとき、市販の有名で老舗の味噌屋さんの味噌を買って、それをタネ味噌にしたらよいかと思うかもしれません。しかし残念ながら、市販の味噌の多くはタネ味噌にはなりません。なぜならば、市販の味噌は製品化の過程のなかで、もともと生きていた菌たちは殺菌され、死滅されているからです。
商品になった味噌は殺菌されている
味噌は発酵食品です。発酵ということは、菌の働きがあり、菌が活躍した結果できあがるのですが、発酵する過程必ずでるのが発酵ガスです。菌たちが生きている証拠です。さてどうでしょうか。市販の味噌はポリ袋やプラスチック容器に入れられ、常温でお店の棚に並んでいます。なおかつ賞味期限がついています。
もし菌たちが生きていたら発酵ガスで膨張して袋がパンパンに膨れ上がってしまうか、容器の蓋がはずれるなど密閉性が失われてきます。商品としてはとても不安定なものになります。そのための殺菌が欠かせないのです。特殊な例になりますが、まれに味噌の容器または袋に特殊なガス排気口(空気弁)がついたものがあります。このような味噌は未殺菌であることがあります。ぜひ探してみてください。